「人工知能」という言葉が生まれた時代
1950年代、コンピュータがようやく普及し始めた頃、人類は「機械は人間のように考えられるのか?」という問いに本格的に挑み始めました。
この時期、「“Artificial Intelligence(人工知能)”」という言葉が初めて公式に使われたのが 1956年のダートマス会議 です。
ハーバード大学のマッカーシー、ミンスキー、クロード・シャノンらが集まり、
「人間の知能を機械で再現できる」というアイデアを議論したこの会議は、まさにAI研究の出発点といえます。
アラン・チューリングの「チューリングテスト」
その少し前、1950年に数学者アラン・チューリングは
「機械は思考できるか?」という論文を発表し、
チューリングテストという概念を提唱しました。
これは、人間が会話相手が人か機械かを見分けられなければ、
その機械は“知能を持つ”とみなせるというテストです。
今のChatGPTのような対話型AIも、この発想を基礎にしています。
初期のプログラムたち
1950〜60年代には、実際に“知能”を持つように見えるプログラムが次々誕生しました。
- ロジック・セオリスト(Logic Theorist):数学の定理を証明できる初期AI(1955年)
- エリザ(ELIZA):人間のカウンセラーのように会話できるプログラム(1966年)
特にELIZAは、人々に「機械と会話できる!」という衝撃を与え、
AIへの期待を一気に高めました。
夢と希望に満ちた“ゴールデンエイジ”
当時の研究者たちは「数十年以内に人間の知能を超える機械ができる」と本気で信じていました。
政府や大学から巨額の資金が流れ込み、AI研究は一気に加速。
この時代は後にAI研究のゴールデンエイジと呼ばれます。
まとめ
1950〜60年代は、AIが「SFの夢」から「学問」として形を持ち始めた時代。
チューリングの理論、ダートマス会議、初期プログラムの登場が、
今日のChatGPTや画像生成AIの原点となっています。
次回は、「AI冬の時代」と呼ばれる停滞期に入る70年代〜80年代を紹介します。
期待が高まりすぎたAIが、なぜ急ブレーキを踏むことになったのか?
歴史の転換点を一緒に見ていきましょう。

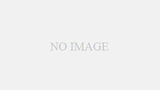
コメント